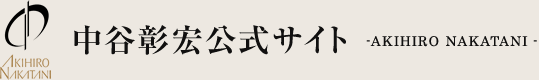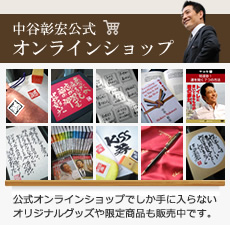【大阪校】体験塾(59)
「自由が好きな人は、現代アートと和食が好き。/アンゼルム・キーファー:ソラリス展 in 二条城+和食展 in 京都文化博物館」
6月15日(日)
田村信之
寿司はおにぎりだったと聞いて、驚きました。
ゆうこりんがカウンターに入ると、染付の大皿に盛られた天ぷらから高級な香りがしました。
佳葉
初の大阪校で、品格と躍動の刺激シャワーをいただきました。
冒頭から、二条城での履き替え用の靴下を忘れ、その後矢継ぎ早に失敗、京の都で、頭が真っ白になりました。
助けてくださった恵子さんの懐の深さと優しさに、待っていてくださった先生と塾生の皆様に、涙が出ました。復習の大切さと、荷物は最小限の意味を、痛いほど刻みました。
佳葉
和食が博物学であるとは、考えたことがなかったです。
調理法ではなく、食材と調理器具のバリエーションが、無限でした。卑弥呼の膳が、思いの外、豊富でした。標本作りという家業の手伝いが、和食につながっていたことが、驚きでした。ここで、博物学と繋がりました。
佳葉
キーファー作品の暗闇と希望のレイヤーを、間近で感じることができました。薄暗さの中で、たわわに実る黄金の小麦には、豊穣の希望がある一方で、その穂先は、怒りに満ちていました。麦刈りが死のメタファである限り、刈取り前の光景は、死に向かうユダヤ人虐殺の記憶と繋がっていました。キーファーの引用するツェランの詩「死のフーガ」の中の「黒いミルク」とも繋がっていました。一方、向日葵の作品には、地表に置かれた種子に、希望がありました。頭をたれたシワシワの花が、俯瞰しているようにも、託しているようにも見えました。小麦畑も、向日葵も、キーファーが敬愛するゴッホのオマージュでした。
佳葉
自然光が思いの外、暗く感じました。しばらくすると目が慣れてきて、オクタビオパスの顔も、荒ぶる、繊細な筆のタッチも、浮かび上がってきました。なぜ自然光にこだわったのか。光は、最初から与えられるものでなく、暗闇の中から自分で見出すもの、自分で見ようとするから見えるもの、メッセージを二条城で受け取りました。
佳葉
靴べらを胸元にしまってから、靴紐を一度ほどき、結び直す先生の所作の美しさに、「履く流儀」を学びました。