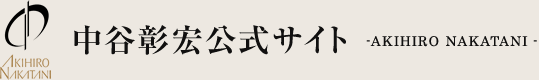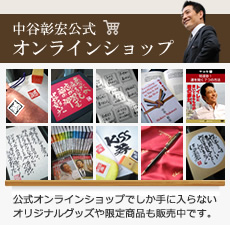【東京校】美意識塾(78)
「どこが工夫されているかに気づく7つの方法」
1月4日(土)
卓也
『小説力』が面白すぎました。
こんな切り口で、近代文学を分析するなんて!
高校でも大学でもこんな授業があれば、生徒は楽しくて仕方ないはず。
最高でした。
佳葉
文壇諸家ランキングで、一次資料を用意してくださったことに感動しました。
菊池寛の交友関係の広さもわかります。日本人のランキング好きもわかります。
コンプライアンスなど言われないこの時代、赤裸々に独断と偏見?を語ってもなお、人が集まってきたのは、多くの人が、「このへんでいいか」と手を放し、自分を優先する場面でも、彼は最後までそうはしなかったからではないのか、と思いました。女性作家の未来に対しては、意外と手厳しかったです。
佳葉
クジャクの冠羽を通して、洞察力を学びました。作品のぱっと見のインパクトと、近寄った時の細密度の両方を味わえることが、深さになります。洞察には、観察するだけでなく、知識も必要なことを感じます。植物画家の友人は、「目はみたいようにしか見ないから」と、RHS FlowerShowでGoldを取った後も、植物の構造を学びに、東大の植物分類学の授業を聴講していました。ミニチュアも同じでした。ざっくりは自己満で、洞察は対話でした。これが深掘りでした。
佳葉
アルポルトで、先生が、鏡ごしに六甲山を映された写真が、ずっと焼きついています。
卵型の鏡に映る、ルーペでみるような、幻想を見るような、色合いと拡大感。
貴族を想像させるフレームのカッティング。
画家である先生の視点が、ラスメニーナスの鏡の表現とつながりました。
クリエイティブであるということは、表現の前に、どれだけの視点と意識が、脳の中でうごめいているかでした。